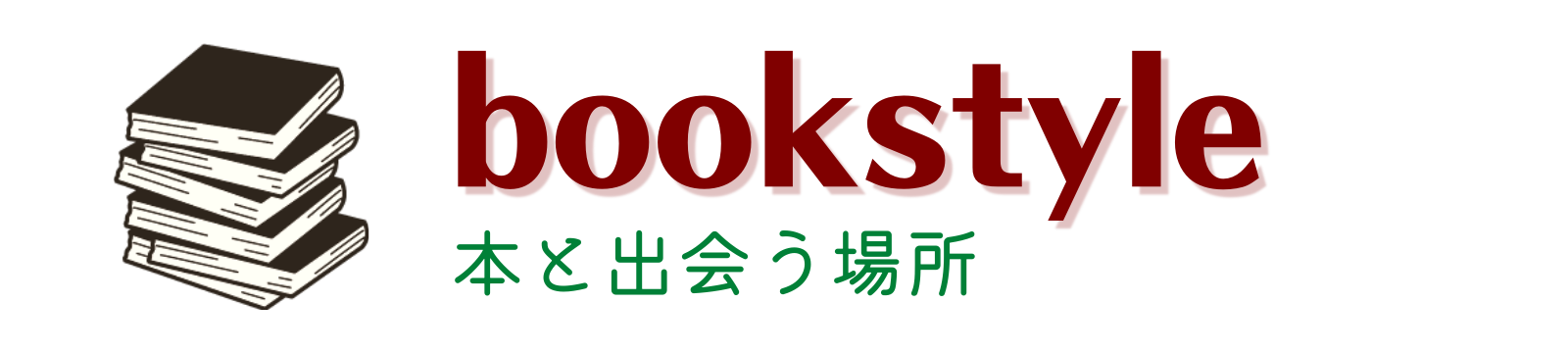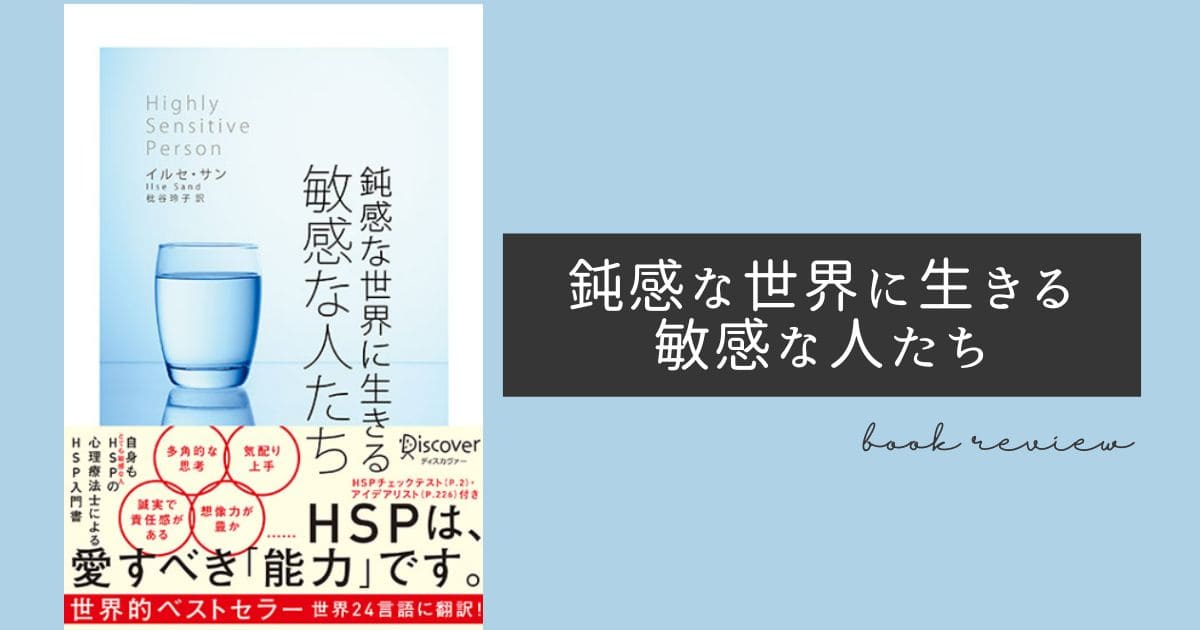今回ご紹介する本は、イルセ・サン著『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』です。
近年、メディアなどでも聞く機会が増えてきた「HSP」という言葉。
HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の頭文字をとった言葉で、日本語で簡単にいえば「とても敏感な人」を意味します。
人が密集している場所にいると異様に疲れたり、芸術作品に強い感銘を受けたり、ニオイや光などで気分が悪くなってしまったり…。
これらは、HSPがもつ特徴のほんの一部です。
世の中では、こういう気質のある人は「神経質」「傷つきやすい」など、どちらかというとネガティブにとらえられがちでしょう。
実際、HSPの人は自身の「生きづらさ」に悩むケースが多いと言われています。
実は、この記事を書いている筆者もHSP気質があり、そんな自分と向き合うための本を探していたところ、今回ご紹介する書籍『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』と出会いました。
本書を初めて目にしたときは救われたような気持ちになりました。
この本を書いたイルセ・サン氏は、デンマークの心理療法士。
ご自身のHSP気質と向き合いながら、HSPで悩む人のカウンセリングを行っているそうです。
私はこの本を読み、考えた結果、いまではこういう気質をプラスにとらえて、自分にとってムリのない生き方を選ぶことが大切なのだと実感するようになりました。
自分はHSPじゃないかと悩んでいる人や、HSPの生きづらさを何とかしたいと思っている人に、ぜひ読んでみてほしい一冊です。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』概要
◆タイトル
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』
◆著者
イルセ・サン
◆出版社
ディスカヴァー・トゥエンティワン
◆発売日(初版)
2016年10月22日
目次
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』の構成は、以下の通り。
- 第1章 鈍感な世界に生きる「敏感な人」とは
- 第2章 「敏感な人」が抱えやすい心の問題
- 第3章 「鈍感な人たち」とうまく付きあうには
- 第4章 「敏感な自分」とうまく付きあうには
前半では、敏感な人(つまりはHSPのこと)とはどのような人なのかや、HSPが抱えがちな悩み・トラブルなどが紹介されています。
また、内容が進むにつれて、HSPである自分と上手に向き合いながら、楽に生きていくためのヒントが掴めるようになっています。
以下では、本書で書かれていることを大まかに紹介しつつ、私自身がこの本を通じて得た学び・考えたことなども語っていきたいと思います。
著者はどんな人?
イルセ・サン氏のプロフィールです。
心理療法士。デンマークのオーフス大学で神学を学び、C・G・ユングとキルケゴールに関する修士論文を執筆。また、いくつかの心理療法的アプローチの訓練を受けており、デンマークの心理療法協会の会員でもある。数年間、デンマーク国教会の教区司祭を務め、現在はスーパーバイザー、トレーナー、講演者、セラピストとして活動している。
Amazon
ご自身もHSPで、HSPならではのさまざまな悩みを抱え、乗り越えてきた経験をお持ちだそうです。
本書のおおまかな内容【HSPとは何か?】
HSPとは、アメリカ人心理学者が提唱した概念
HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の頭文字をとった言葉で、簡単にいえば「ものすごく敏感な人」を意味します。
HSPの概念が生まれたのは1996年。
アメリカの心理学者でセラピストのエレイン・N・アーロンという女性博士によって提唱されたのがはじまりとされています。
ちなみに、エレイン博士の夫のアーサー・アーロン博士は、吊り橋を一緒にわたる男女は恋愛に発展しやすいという「吊り橋効果」の実験を行った人なのだとか。
心理学の世界では名高いご夫婦のようです。
アーロン博士によれば、世の中の5人に1人はHSPで、決して珍しいものではないとのこと。
イルセ・サン氏著『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』では、このアーロン博士が唱えるHSPの特徴や、HSPの人が抱えがちな悩みについて、わかりやすくまとめられています。
HSPは生まれもった気質であり、病気ではない
本書では「HSPというのは生まれつきの気質であって、病気ではない」ということを前提に語られます。
HSPの人には、たとえば以下のような特徴があります。
- 人が密集している場所にいると異様に疲れる
- 映画や音楽、本などの芸術作品で強く心が動かされてすぐ泣く
- ニオイや光などの外部刺激に弱く、気分が悪くなってしまう
- 他人の機嫌や気持ちが、ちょっとした仕草や表情などからわかってしまう
他の人なら我慢できたり見過ごせたりすることであっても、非常に敏感に反応することがHSPの特徴です。
また、HSPは独自の精神世界をもって深く思考することを好む傾向にあり、一見「内向的な人」とも似たようにとらえられがちです。
ただ、HSPにとって「内向的」というのは、あくまでも「気質」のひとつでしかありません。
このほか、「良心的」「創造的」「影響を受けやすい」「感情移入しやすい」といったさまざまな要素が複雑に絡み合っているのがHSPとされています。
そして、本書では「HSPのなかには内向的ではない、つまり外交的な人も存在する」ということが書かれています。
内向的でないHSPは大きく2つのタイプに分かれる
HSPには共通する気質の方向性がありますが、全員がまったく同じような考え方・行動をとるわけではありません。
たとえば、以下のように一見するとHSPには見えない人も存在するといわれています。
- 外交的なHSP
- 刺激を求めるHSP
それぞれについて詳細を説明します。
外交的なHSP
HSPの70%は内向的、そして残りの30%は外交的といわれています。
HSPは物静かで一人で過ごすことを好む人が多いですが、その一方で、たくさんの人に囲まれて過ごすほうが心地よかったり、大勢の中の1人でいることに安心や親しみを覚えるタイプのHSPがいても、なんら不思議ではないとのこと。
本書によれば、大家族で育ったり、学生時代にシェアハウスなどで大勢の人と一緒に生活したりしていると、外交的なHSPになる可能性が高まるようです。
刺激を求めるHSP
HSPのなかには、冒険心が旺盛で、退屈を苦手とし、自分から刺激を求め続けるタイプの人もいるのだそう。
このタイプの人はルーティンワークが苦手だったり、同じ場所に居続けるのを極端に嫌がったりし、危険やスリルに飛び込む傾向があります。
ただ、一見外交的に見える人でも「過度に刺激を受けやすい」HSPの気質をもっている以上、自分の中に情報があふれて疲弊しやすく、自分自身のバランスをとるのが非常に難しくなりがち。
本書では「アクセルとブレーキを同時に踏むようなもの」と書かれており、言い得て妙だなと感じました。
HSPはどうして生きづらいのか?
本書では、多くのHSP気質をもつ人が「生きづらい」と感じてしまう理由がわかりやすく解説されています。
ここでは、簡単に3つのポイントにしぼってまとめます。
①:すぐ疲れてしまう→情報を受け取り過ぎるから
本書では、HSPの気質のひとつを「一度に多くの情報を吸収できる」と表現しています。
HSPは敏感な神経をもっているがゆえ、細かいところまで感じ取り、情報をもとにさまざまな思考や空想を広げます。
そのため、頭のハードディスクがすぐにいっぱいになり、過度に刺激を受けたと感じやすいのです。
本書中に、このような文章があります。
知らない人といると、30分か1時間でもうキャパシティー・オーバーになってしまうのです。(中略)楽しいパーティーであっても、キャパシティーを超えてしまって、たとえパーティーの佳境でも、退散しなくてはならなくなります。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』p42、p44
このお話、個人的にとても共感します。
他の人が長時間の集まりやパーティーでも平気で楽しんでいても、私は1時間も経てば疲労感でいっぱいになります。
その場を離れて一人になった瞬間の安堵感たるや…。
でも、現実社会だと、そういう人間は「つき合いが悪い」「社交性がない」「ぼっち」みたいに言われるんですよね…。
それが、HSPが感じるつらさにもつながっているように思います。
②:環境に順応できず苦痛を感じやすい→音やニオイなどにも敏感だから
HSPの特徴のもうひとつは、「不快な音やニオイ、視界に入るものなどを気にし過ぎること」だとされています。
たとえば、HSPは以下のようなことが気になります。
- 喫煙者の持ち物や自宅の家具に染み付いたタバコのニオイ
- マンションの他の住人が歩く小さな音
- カフェで流れる気分に合わないBGM
これらはHSPでなくても多少は不快に感じるかもしれませんが、「まあいいか」「仕方ない」とガマンしようと思えばできる人が多いのではないでしょうか。
しかし、HSPは一度不快に感じてしまうと、やり過ごしたり気をそらしたりがなかなかできません。
耐えがたいほどの苦痛におそわれて神経のバランスを崩してしまうことさえあります。
現実社会だと、そういう人は「わがまま」「自分勝手」「我慢強さがない」などと言われてしまいがち。
面と向かっては言われなくても、日本では、そういう人間を歓迎しない環境や風潮があるように思えます。
こういったことから、HSP気質の強い人は、心身が悲鳴をあげているのに「自分はダメな人間だ…」と思い込んでしまう要因になります。
③:他人や状況に感情移入して疲弊する→共感力が高過ぎるから
イルサ・セン氏は、HSPには「共感力が強い」という特徴もあると述べています。
他人に感情移入できることから「気配り上手」や「気が利く」といわれることも多いのがHSPの強みです。
この特性はサービス業などで力を発揮できる一方、他者の気持ちに左右されやすく、相手の苦しみや嫌な感情まで自分事のようにとらえてしまうところがあります。
- 誰かがケンカをしている場が非常に苦痛
- 人をちょっと傷つけてしまったとき、必要以上に自分自身も傷つく
- 怒りの刺激を受けすぎると、自分の内面への語りかけができなくなり急に無気力になる
こうした傾向があるのも、HSPならではだそうです。
私自身も、昔から人の気持ちに反応しがちなのを自覚しています。
場の空気感の変化や、相手の感情の動きがなんとなくわかってしまうので、疲れてしまいます…。
このほかにも、本書ではHSPが抱えがちな悩み、苦しみにはちゃんと理由があることが説明されています。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』を読んで考えたこと【HSPが楽に生きるには?】
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』では、HSPが楽に生きていくためのポイントがいくつも紹介されています。
そのなかから自分がとくに重要だと感じたこと、実践してよかったことなどをまとめます。
①:敏感で繊細な自分を認める
繰り返しになりますが、HSPは悪いものではなく、あくまでも生まれもった気質の一種です。
でも、おそらくHSPの人は、敏感で繊細な自分をどこかでダメだと思い込んでしまっているのではないでしょうか。
子どもの頃から「外交的な人=優れている」「繊細で神経質な人=治すべき悪いこと」という教育を受けていたり、社会の風潮があったりすることが、その要因のひとつではないかと個人的には感じています。
しかし、この本でも書かれているのですが、そもそも「内向的」とは、タフで外向きの人が自らの優位性をアピールするために作り出した言葉や概念とも考えられます。
実際には、敏感かつ繊細でなければ見えないものや、気づかないことがたくさんあるんです。
深く物事を考える力があり、他の人が見過ごしてしまう喜びにも気づけるのは、HSPの強みです。
その事実を冷静に見つめて、HSPのポジティブ面に注目することの重要性を、イルサ・セン氏は語っています。
HSPは、より恐怖を感じたりするだけでなく、ほかの人よりも喜びを深く感じ、特別な才能を持つグループに属するとされています。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』p30
②:ありのままの自分を認めてくれる人とつき合う
本書でもう一つ印象的だったのは「HSPは自尊心が低くなりやすく、愛されるために優秀な自分であろうとする」という記述でした。
ですが、著者は「愛される努力をするより、ありのままの自分を受け入れるほうが大切だ」と説明しています。
この辺りの話題は、ズッシリと胸に響きました。
プライベートな話になりますが、私にとって「HSPでもまあいいか」と思えるきっかけとなったのは、夫との出会いです。
夫はのんびりとしたタイプで、私から見たら「鈍感」なところもある人。
ただ、私がHSPで苦しくなってイライラしたり、ふさぎこみそうになったり、泣いたりしても、決して否定したり見捨てたりしません。
そういう人が身近にいる安心感を得たことで、自分を認められる度合いが増えました。
こうした経験から感じるのは、「合わない人とムリしてつき合う必要はない」ということです。
昔の私には「誰とでもうまくやらなくては」という気持ちが強くありました。(今もゼロではないですが)
でも、刺激を感じやすく人との関わりで疲れやすいHSPが、周りにばかり合わせようとするのは苦痛でしかないのですよね…。
なので、私はムリして自分を偽り続けなくてはならない環境なら一人のほうがいいと思うようになり、集団に身を置かなければならない場面でも、変に周りに合わせるのはやめました。
「一人好きキャラ」も隠さないようにして、疲れる環境からは意識的に離れるように心がけています。
まずは、自分の心を守ることが大切なのだと思えるように。
③:自分にとって居心地のいい生き方を真剣に考える
本書の一節に、以下のような記述があります。
HSPは環境が整っていない状況下では困難に見舞われますが、一方で、適切な環境下では、HSPでない人たちよりも、その環境を楽しめるということが研究で裏付けられています。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』p32
私はこのことからも、HSPは「自分に合う環境を見つけること」が非常に大事なのだとあらためて感じました。
また、自分が感じる生きづらさは、自分で克服していくことも必要なのだと思います。
私が悩んで導き出したその最良の方法は、「自分にとって居心地のいい生き方を選択すること」です。
これを読んでくださっているあなたは、現在の自分の生き方に満足できているでしょうか?
もし、窮屈さや居心地の悪さ、モヤモヤした感覚があるのなら、それを少しずつでも変えていくことを考えてみてほしいです。
「いや、そんなの変えられないし…」「立場や責任とかもあるし…」と思う方もいるでしょうが、もしかすると、その裏には「変化することへの怖れ」や「面倒くささ」があるのかもしれません。
何かを変えるためにはものすごくエネルギーも必要としますが、自分の生き方を決められるのは本来、自分以外にはいません。
もし現状を変えるために逃げることを選ぶとしても、不満を抱えたまま止まっているよりも意味と価値があると思います。
ちなみに私は自問自答した結果、「外部刺激で疲れる→マイペースで仕事をするほうがよさそうだ」と思い、働き方を会社員からフリーランスに変えました。
成功する保証はなくても、誰かと比較する必要はありません。
本書でも語られている通り、自分にとって居心地のいい生き方をすることで力を大きく発揮できるのは、深く思考するHSPの特徴なのだと思います。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』まとめ
最近はHSPであることを公表する芸能人・タレントも増えて、ちょっとずつHSPが認められるようになってきたと思います。
でも、自分の心が理解・納得していなければ、本当の意味で生きづらさの克服にはなりませんよね。
『鈍感な世界に生きる 敏感な人たち』では、「鈍感な人たち≒HSPではない多くの人々」たちとうまくつき合うための方法・ポイントが書かれています。
ほかにもHSPを扱った漫画や書籍はありますが、この本の内容は難しすぎず、それでいてHSPが直面する具体的なケースと、困難を乗り越えるための考え方まで書かれているので、1冊でいろいろなことを感じられると思います。
私自身、それまで自分だけで悩んでいたことも、これを読んで腑に落ちたところがありました。
著者が作り上げた、より精度の高いHSPの自己診断テスト&解説も付属しているので、HSPで悩んでいる人には参考になるはずです。
HSPであっても、決して自分を卑下したり自信を無くしたりする必要はないのですよね。
自分が自分らしくいられる状態をつくって、感じている生きづらさから自分を解放させてほしいなと思います。


さまざまな観点からHSPの理解を深められる本を紹介しているので、ぜひチェックしていただければと思います。