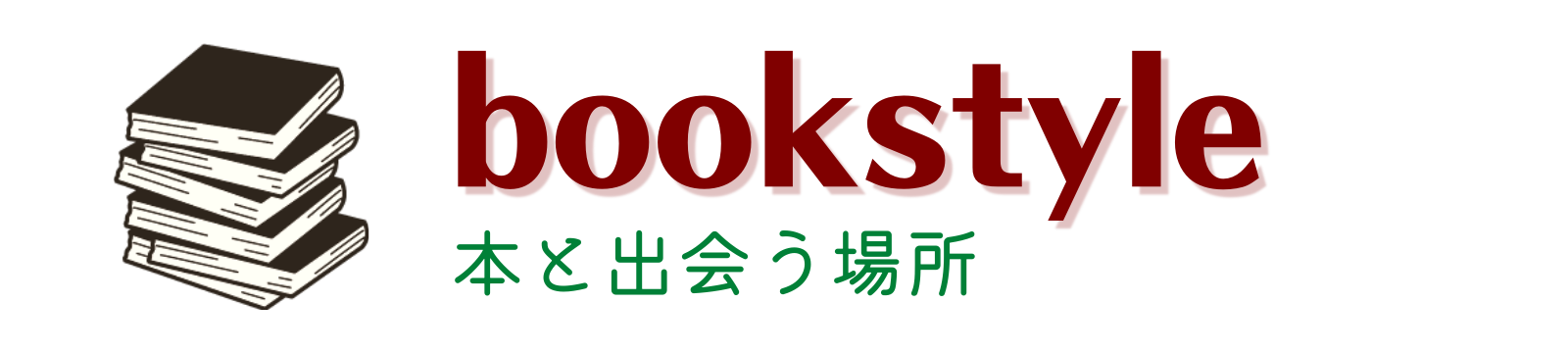皆さんは「本屋大賞」という言葉を聞いたことがありますか?
「いつも欠かさずチェックしてるよ!」という人もいれば、「何それ?」という人もいるかもしれません。
「本屋大賞」とは、全国の書店員さんたちが「売りたい!」「おもしろかった!」と思う本を選び、投票によって決まる文学賞。
2022年度で19回目を迎え、受賞作品やノミネート作品は映画化・アニメ化などにつながることも多く、年々注目度も高まっています。
この記事では、そんな本屋大賞とはいったいどんなもの?という基本情報から、本屋大賞の受賞作品に注目していただきたい理由まで、わかりやすく解説しています!
面白い本に出会いたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね!
本屋大賞とは?
全国の書店員さんが「一番売りたい本」を決める文学賞!
本屋大賞とは、「NPO法人 本屋大賞実行委員会」が運営する文学賞です。
本屋大賞の最大の特徴は、通常の文学賞のように審査に著名な作家・文学者が参加せず、全国の書店員(オンライン書店を含めた新刊を扱う書店員)さんたちが「おもしろかった!」「お客様に薦めたい」「売りたい!」と思う本を選び、投票すること。
その結果によって、ノミネート作品と受賞作が決定されます。
「第1回本屋大賞」が開催されたのが2004年。
以後、年に1回開催されており、2022年で第19回を迎えています。
もともと本屋大賞は「書店店頭でのお祭りになるイベント」として創設されたのだそうです。
ですが、本と読者に最も近い立場の書店員が決めるユニークな文学賞として注目を集め、徐々に規模を拡大。
参加する書店員の数は年々増え、世間の知名度も高まっています。
どんな本が選ばれる?過去の大賞受賞作は?
本屋大賞の選考対象となるのは、過去1年間に刊行された日本の小説です。
つまり、古い小説や、小説以外の本(ビジネス書、新書、マンガなど)は対象にはなりません。
ここで過去の大賞受賞作を一覧でご紹介します!
| 年度 | タイトル | 著者 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 『同志少女よ、敵を撃て』 | 逢坂冬馬 | 早川書房 |
| 2021 | 『52ヘルツのクジラたち』 | 町田そのこ | 中央公論新社 |
| 2020 | 『流浪の月』 | 凪良ゆう | 東京創元社 |
| 2019 | 『そして、バトンは渡された』 | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
| 2018 | 『かがみの孤城』 | 辻村深月 | ポプラ社 |
| 2017 | 『蜜蜂と遠雷』 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
| 2016 | 『羊と鋼の森』 | 宮下奈都 | 文藝春秋 |
| 2015 | 『鹿の王』 | 上橋菜穂子 | 角川書店 |
| 2014 | 『村上海賊の娘 上巻』 | 和田竜 | 新潮社 |
| 2013 | 『海賊とよばれた男』 | 百田尚樹 | 講談社 |
| 2012 | 『舟を編む』 | 三浦しをん | 光文社 |
| 2011 | 『謎解きはディナーのあとで』 | 東川篤哉 | 小学館 |
| 2010 | 『天地明察』 | 冲方丁 | 角川書店 |
| 2009 | 『告白』 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 2008 | 『ゴールデンスランバー』 | 伊坂幸太郎 | 新潮社 |
| 2007 | 『一瞬の風になれ』 | 佐藤多佳子 | 講談社 |
| 2006 | 『東京タワー―オカンとボクと、時々、オトン』 | リリー・フランキー | 扶桑社 |
| 2005 | 『夜のピクニック』 | 恩田陸 | 新潮社 |
| 2004 | 『博士の愛した数式』 | 小川洋子 | 新潮社 |
「翻訳小説」と「発掘」部門も
上記で紹介した通り、本屋大賞の対象となるのは「小説」です。
しかし、本屋大賞が続いていくなかで、現在では「翻訳小説」部門と「発掘」部門も設置されています。
それぞれの対象作品は以下の通り。(2022年度の場合)
- 翻訳小説部門:2020年12月1日〜2021年11月30日に日本で刊行された翻訳小説
- 発掘部門:ジャンルを問わず、2020年11月30日以前に刊行された作品
通常の本屋大賞はあくまでも直近に発売された本の中から選ばれますが、発掘部門は「時代を問わず」というのがポイントですね。
大賞は決定されず、各作品の投票数で順位が決まります。
さらに、2016年からは、発掘本の中から「これは!」と思う1冊を実行委員会が選出し「超発掘本!」として発表されています。
【過去の「超発掘本!」選出作品】
- 2022年:『破船』吉村昭(著)
- 2021年:『ない仕事の作り方』みうらじゅん(著)
- 2020年:『無理難題が多すぎる』土屋賢二(著)
- 2019年:『サスツルギの亡霊』神山 裕右(著)
- 2018年:『異人たちの館』折原 一(著)
- 2017年:『錯覚の科学』クリストファー チャブリス、ダニエル シモンズ(著)
『破船』が文庫化されたのは1985年。まさに時代を超える作品ですね。通常のノミネート作品と違って、ややマニアックな本に出会えるのも面白いです。
本屋大賞の選考方法・スケジュール
選考方法は?
本屋大賞の選考方法は、以下の通りです。
対象作品:過去1年間に刊行された日本の小説
審査員(投票参加資格者):新刊を扱っている書店の書店員(アルバイト、パートも含む)
選考方法:1次投票で1人3作品を選び投票
↓
選出された上位10作品のうちから2次投票をおこない、大賞を決定
なお、2次投票では、投票参加者はノミネートされた10作品をすべて読んだ上で推薦理由を記載し、投票。
3作品に順位をつけて投票し、順位に応じた点数をつけて集計され、大賞が決定します。
選考スケジュールは?いつ発表される?
本屋大賞は、毎年以下のスケジュールで開催されています。
前年12月:1次投票スタート
1月上旬:1次投票締切
1月下旬:ノミネート作品発表→2次投票スタート
3月上旬:2次投票締切
4月上旬:本屋大賞結果発表!
本屋大賞にはノンフィクション大賞もある?
実は、本屋大賞では2018年より「ノンフィクション」作品についても投票が行われています。
正式名称は「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」です。
本屋大賞とヤフー株式会社の協力により開催されており、2022年度で第4回目を迎えています。
投票の対象作品となるのは、過去1年間に日本で発行された国内作家によるノンフィクション本。
2021年の結果は以下の通り。
大賞
『海をあげる』上間陽子(著)
ノミネート作品
『あの夏の正解』早見和真(著)
『キツネ目 グリコ森永事件全真相』岩瀬達哉(著)
『ゼロエフ』古川日出男(著)
『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』河野啓(著)
『分水嶺 ドキュメント コロナ対策専門家会議』河合香織(著)
小説以外の本でも引き込まれる作品はたくさん。ぜひ注目していただきたいです!
本屋大賞が「やらせ」と言われる理由は?
最近では書店でのフェアはもちろん、いろいろなメディアで取り上げられることが増えた本屋大賞ですが、一方では「本屋大賞は所詮やらせでしょ?」など批判の声も聞こえてきます。
どうやら以前、著名な作家さんが本屋大賞に対して厳しい私見を発表したこともあって、本屋大賞に対してネガティブなイメージを抱く人もいる様子。
私は本屋大賞の裏側はわかりませんが、20回近くも続いている影響力の大きな賞ですし、決して「やらせ」ではないと信じています。
お偉いさん方ばかりが審査にあたる一般の文学賞よりも、身近な書店員さんが選んでくれる本屋大賞のほうがよほどいい!と思う人だっているはず。
ただ、文学賞に一定の権威性を求める人からすれば、本屋大賞は大衆的で質が低い…と判断しても仕方がないのかな、とは思います。
実際、本屋大賞にノミネートされる小説は、読みやすくて親しみやすい本が多いです。(この後、メリットの部分で改めて語ります)
賞の性質上、「難解」で「読む人を選ぶ」ような本は選ばれにくいのですよね。
これは私の意見ですが、「本屋大賞とはそういうものだ」と、エンターテインメント的な気持ちを持って楽しめば良いのではないか?と考えています。
もともと本屋大賞は、書店を盛り上げるための「お祭り」のようなイメージでスタートしたアワードとのことですしね。
本屋大賞は面白い!おすすめする3つの理由
ここまで、本屋大賞の基本情報を紹介してきました。
本屋大賞のノミネート作品は、本が大好きな人はもちろん、あまり本を読む機会がない人、あるいは何を読んでいいかわからない人にこそ、ぜひおすすめしたいと思っています。
以下では、本屋大賞の受賞作をおすすめする3つの理由を紹介します!
メリット①:読みやすい本が多い!
本屋大賞とは別の文学賞で有名なものといえば、多くの人が「芥川賞」や「直木賞」を思い浮かべるでしょう。
これらは歴史と権威ある文学賞ではありますが、受賞作の中には、ややとっつきにくい本も含まれます。(とくに芥川賞は純文学を対象としているので、芸術的過ぎて難解…なんていう声も聞かれることがあります)
それらに対し、本屋大賞にノミネートされる作品は「エンタメ性」を重視したものが多く選ばれる傾向にあり、多くの人にとって読みやすい作品が中心です。
「書店員の方々が、なるべく多くの人に読んでほしい!」と思う作品を勧める賞なので、当然といえば当然ですね。
普段は小説をあまり読まない人や、難しい本に抵抗を感じている人でも、本屋大賞なら親しみやすい作品に出会うことができます。
メリット②:本屋大賞の受賞作品は、映画化など何かと話題に!
本屋大賞の受賞作品は、小説そのものとして注目を集めるのはもちろんですが、その後も映画化・アニメ化など、さまざまな方面で話題になるものが目立ちます。
2020年からの過去10回の大賞作品を見ていくと、そのことがよくわかります。(2022年10月時点)
- 『流浪の月』(2020年)→2022年に映画化
- 『そして、バトンは渡された』(2019年)→2021年に映画化
- 『かがみの孤城』(2018年)→2022年に映画(劇場アニメ)化
- 『蜜蜂と遠雷』(2017年)→2019年に映画化
- 『羊と鋼の森』(2016年)→2018年に映画化
- 『鹿の王』(2015年)→2021年に映画(劇場アニメ)化
- 『村上海賊の娘』→なし
- 『海賊とよばれた男』→2016年に映画化
- 『舟を編む』(2012年)→2013年に映画化、2016年にテレビアニメ化
1作品を除いて、すべてが数年以内に映画化・アニメ化されています!
ちなみに大賞以外のノミネート作品にも、映画やドラマ、アニメなどになっているものはたくさんあります。
(例:『重力ピエロ』『夜は短し歩けよ乙女』『ソロモンの偽証』『罪の声』『コーヒーが冷めないうちに』『騙し絵の牙』など)
他メディアへ展開されるということは、それだけエンターテインメント性があり、多くの人が「面白い!」と思う可能性が高いということ。
あちこちで話題になる機会も多いので、原作となる小説をしっかり読んでおいて損はありません。
メリット③:好きな作家に出会うきっかけになる
「本をたくさん読みたい!」とは思っても、あまりにいろんな本が次から次へと発売されて、いったい何から読めばいいか結局迷って読まずじまい…。
皆さんは、こんな経験がありませんか?
あるいは、自分がどんな本が好きなのか自分でもイマイチわからない、好きな作家さんが見つかればいいのに…なんて思う人もいるかもしれません。
そういう人は、ぜひ本屋大賞の受賞作・ノミネート作品を読んでみていただけたらと思います。
毎年、本屋大賞にノミネートされるのは10〜11作品。
これくらいであれば、気が向いたものをとりあえず読んでみる気になるのではないかな、と思います。
あまり知らない作家さんの本でも、1つや2つくらい自分にフィットする作品に出会えるはずです。
そこから似たテーマの本や同じ作家さんの他作品へ広げていく…そんなふうに本の楽しみ方が広がるのも、本屋大賞に触れるメリットといえます。
まとめ:「本屋大賞」受賞作には面白い作品がたくさんあります!
この記事では、本屋大賞についてまとめました。
「文学賞」と聞くと「何だか難しそう…」と構えてしまいがちですが、本屋大賞の受賞作品・ノミネート作品はエンターテインメント性の高い小説ばかり。
純粋に「面白かった!」「心がほっこりした!」と思える作品にもたくさん出会えます。
本屋大賞はこの先も続くはずなので、ぜひ毎年春の発表時期にはチェックしてみてくださいね。
過去のノミネート作品を少しずつ読んでいくのもおすすめです!